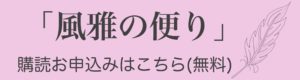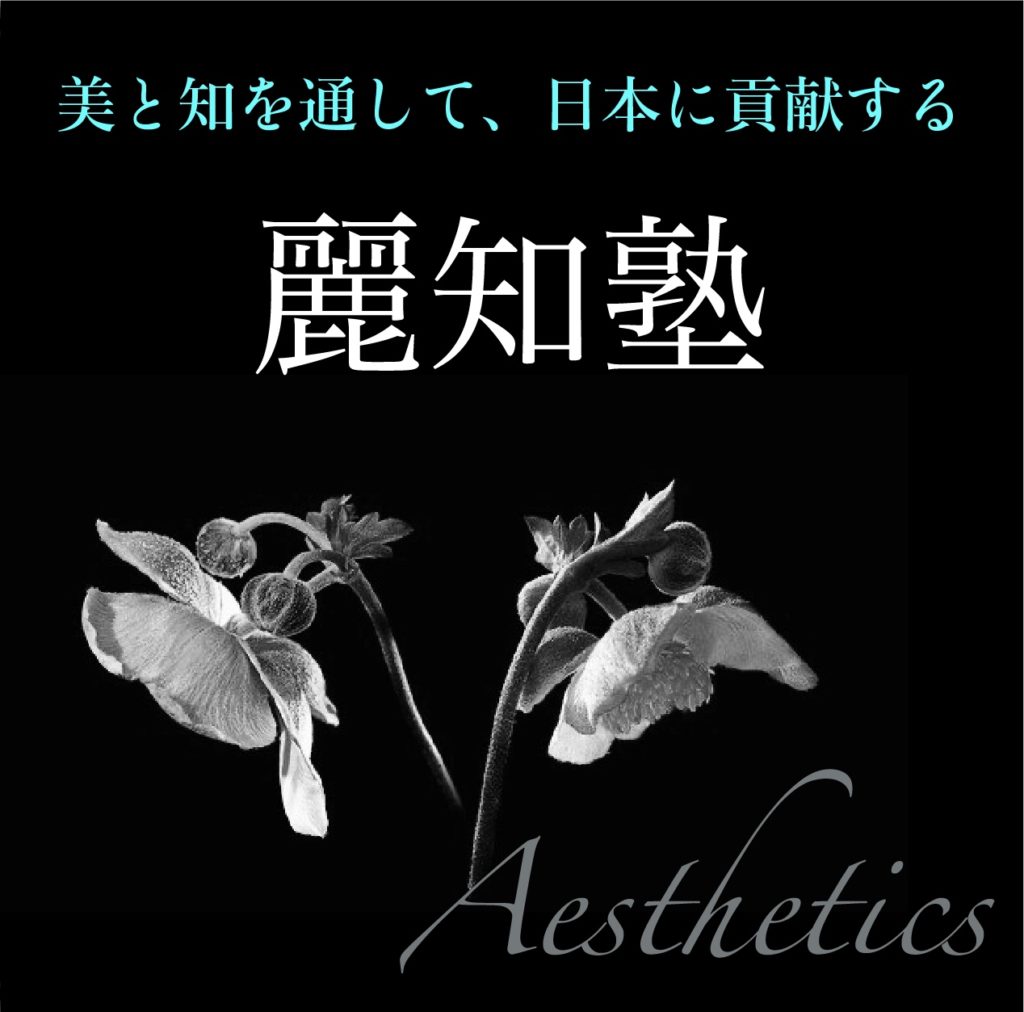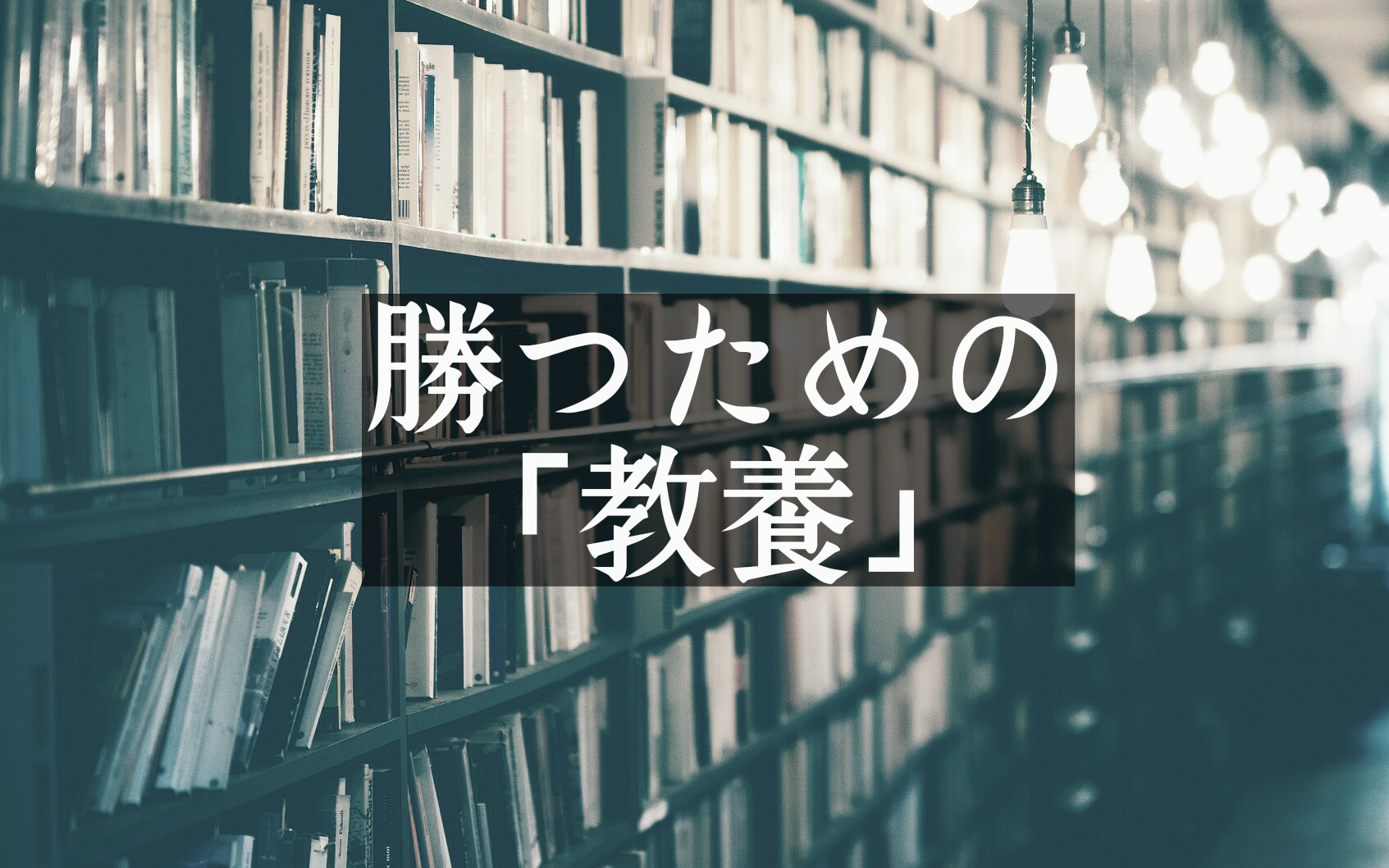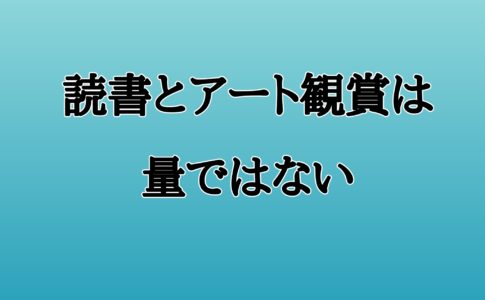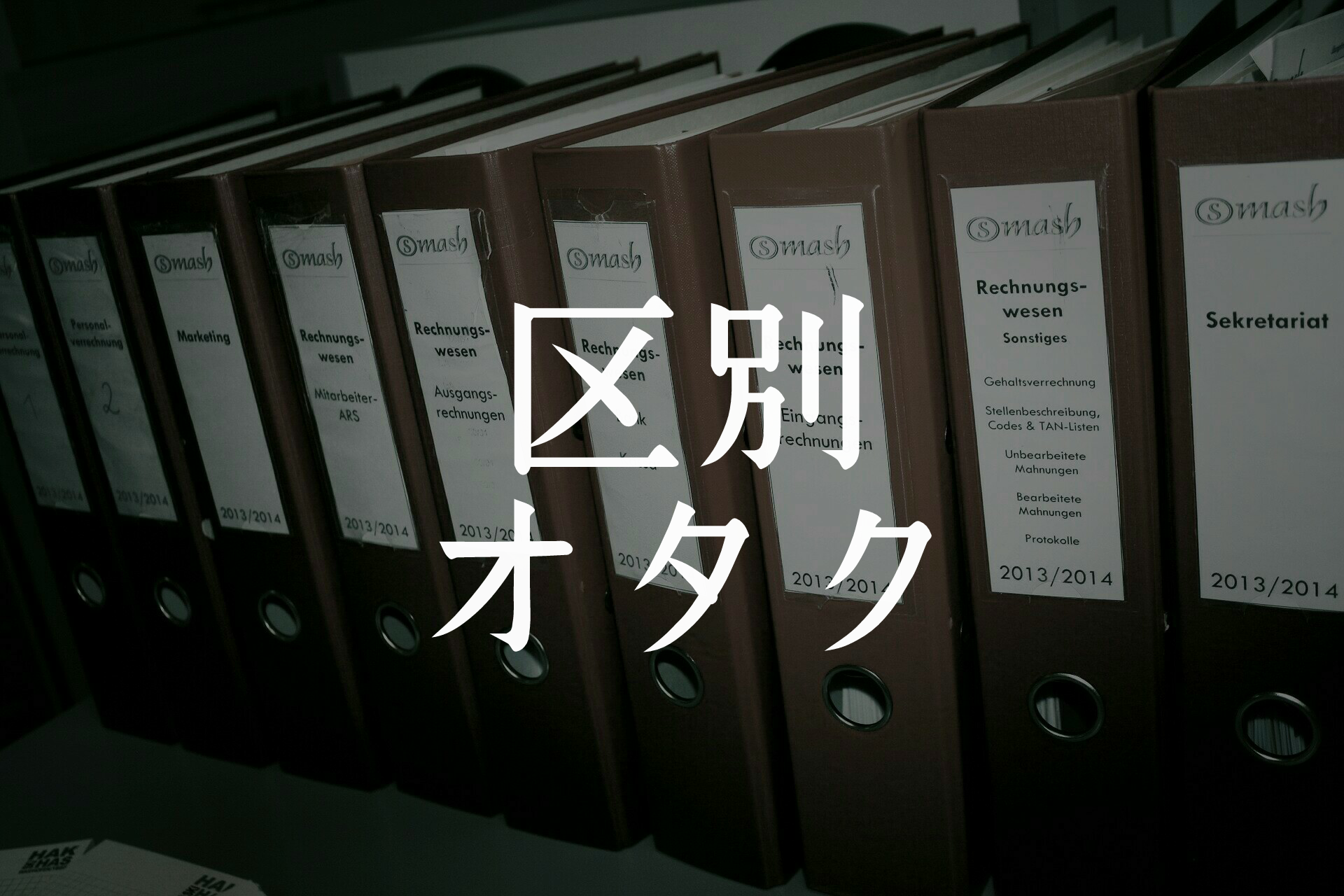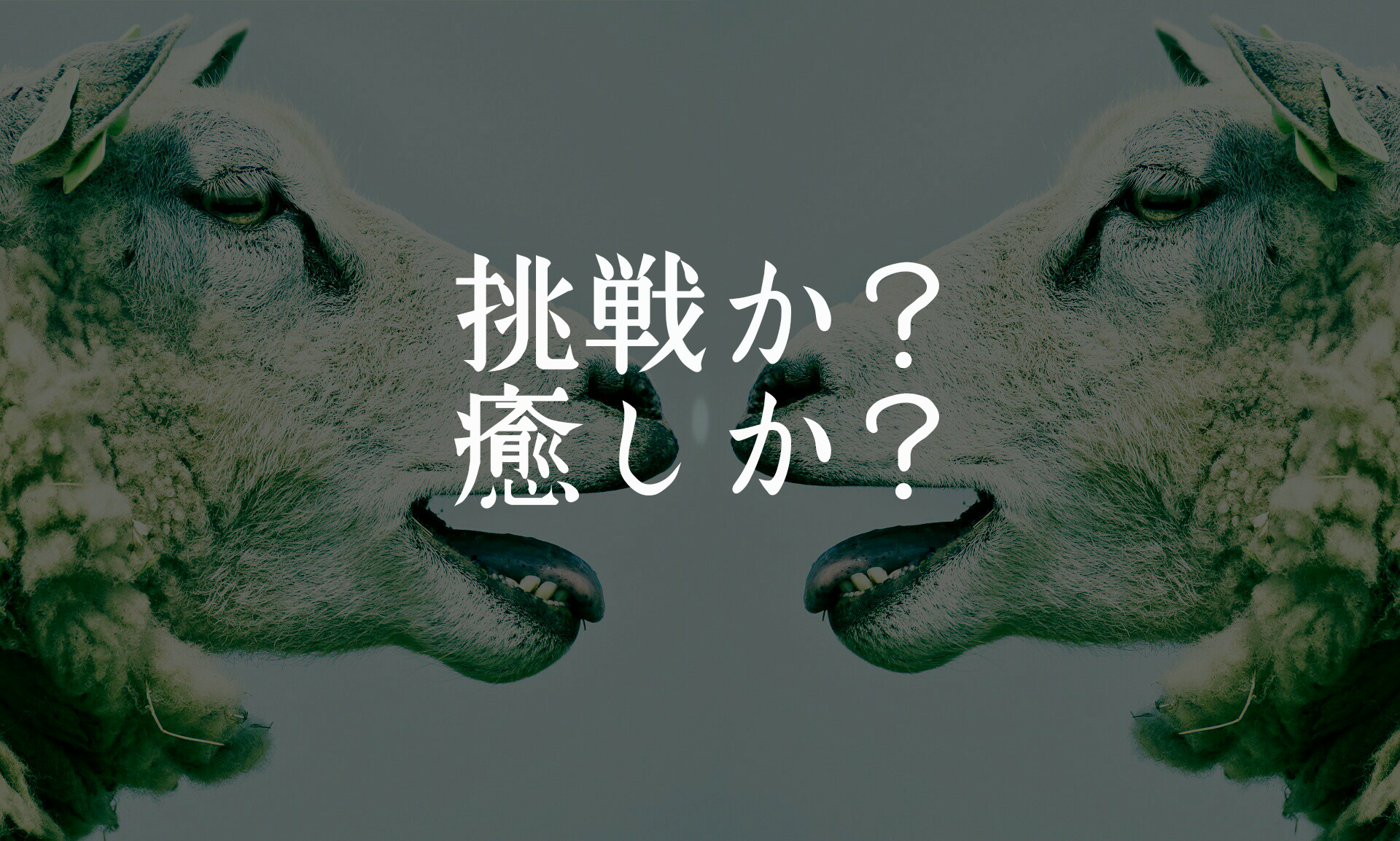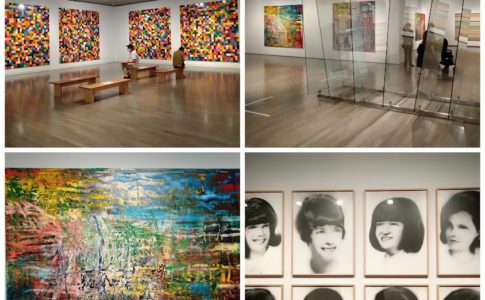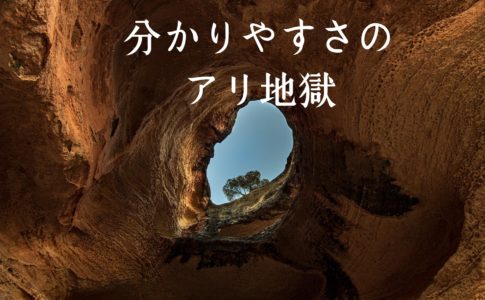アートと言えば、「芸術のための芸術」、つまり何かの目的に創作されたものは真の芸術とは言えないという考え方がある一方、現在では有名ブランドとのコラボレイトや地域おこしや社会活動のためのアートというようなものも増え、実にさまざまに多様化しています。
このような多様化は、アートに限らず、ビジネス、科学、思想の分野で起こっています。
それはコーチングの分野でもです。
多様化は何をもたらすのか?この時代をどう生きるのか?について書いていきます。
コーチングの多様化はなぜ起こるのか?
現在のコーチングは様々な団体が乱立し、他団体との差をつけて特徴を出そうとしています。それにくわえ、それらの資格を取得した人々が、○○コーチング、△△コーチングなど、自分の仕事を競合から区別するために独自の名前で独自の手法を組合わせて行っています。
実はコーチングの世界だけではなく、弁護士、会計士、などのお堅い仕事からアーティストの世界にも起こっていることです。
昔なら弁護士というだけで、よかったわけです。そういう看板を出していれば、ありとあらゆる案件が仕事としてやってくるわけですから、下手に「私は○○の専門家だ」と言うと仕事が限定されて売り上げが減ることになります。
しかし、弁護士というプレミアムな資格であっても、弁護士が必要となる仕事の件数がそれほど増加していなにのに、弁護士資格を持つ人が増え続ければ飽和状態になるのは当たりまえです。
ビジネスはその資格がプレミアムであろうとなかろうと関係ないのです。
実際、弁護士資格を取った人が、弁護士事務所に就職できず、実務経験をたくわえることができなくて、困っているという話を実際に弁護士さんから聞きます。
そうなると、「ただ弁護士です」と言ったところで、お客様が自分を選んでくれる確率が少なくなります。
そこで、○○専門の弁護士とか、○○に強い弁護士などと、強豪との差をみせて自分を選んでもらおうとするわけです。
とくに、後発で独立する人たちは、すでに市場のパイは先行の人達が牛耳っているわけですから、そのような手法で行くしかありません。
アートもそうです。
アーティストになりたい人は世界中に大勢います。しかし、高額で
アート作品を買ってくれる人はそれほどいません。そうなると競争に勝つために強烈な個性と差別化が必要となります。
しかも、アートの場合、偉大な先人とも戦わなくてはいけないわけですから、厳しい世界だと思います。
コーチングも競合が増えた割には、クライアントになる人の数はそれほど増えていない。
そういう場面で、やはり差別化、多様化の道をたどっていると考えられます。
多様化は概念を弱体化する
ブランド概念を強めるための歴史
「芸術」という概念は西洋文化が長い時間をかけて作ってきたものです。
芸術とは何か?
素晴しい芸術とは何か?
芸術とそうでないものの差は何なのか?
さまざまなアーティストや哲学者がその時代ごとに知恵をしぼって考えてきたものです。
そして、さまざま考えてきた「芸術」の考えかたの質を守るために、作品を評価したり、後継者を要請する学校が出来ます。
つまり、基準をもうけることで、芸術とそうでないものを区別し、そうすることで芸術の質を保とうとしました。
ビジネスで言うとブランドです。
ブランドになるためには明確な基準が必要です。(それが、合理的か、公平であるかどうかは別にして)
例えば、今治タオルは厳しい品質基準を設けそれに合致しないものには、ブランドを名乗らせないと徹底しました。これは生産者にとっては負担を強いることなので、最初は反対もありましたが、今は高品質なタオルのブランドとして認知されています。
タオルなんて、どこにでも売っている物です。しかし、他との差を明確にし、それを守ることでブランドになりました。
アートも同じで、「芸術とは○○であり、それ以外の物はダメ!」と明確な基準があれば、「芸術」の価値は揺るがないものになります。
近代以前は芸術の価値はアカデミーや芸術団体が認定していました。これらの機関は芸術の質を守り発展させることを目的としていますので、彼らが認定すれば、それは芸術であるけです。
その価値にたいして、人は安心感をもって鑑賞したり、作品を買ったりするのです。
しかし、昨今のように、差別化、多様化の時代になったらどうなるか?
今治タオルを例にあげると、今治タオルの中にも、いろんなものがあってもいいよね!質が悪くても安い物とか、基準を満たしてなくてもマークがついてれば今治タオルなんだから、それ以外の新しい斬新なものを作ろう!
となったら、今治タオルのブランドの輪郭はあやふやになってしまいます。
これが、概念の弱体化です。
アートもコーチングもタオルの様に物ではないので、数値で計測できないものは基準がもともと曖昧です。
概念の弱体化が起こりやすい物なのです。
だからこそ、今までは先人たちは基準や制度をつくって、アートとは、コーチングとはという概念が弱体化しないように努力してきたのです。
概念の破壊と弱体化
しかし、歴史は破壊と創造を繰り返すものです。
概念は固定化され、強固になると、それから逃れようという動きが起こります。
アートも既存の芸術の概念を壊す動きが、20世紀に起こり、ありとあらゆるアートが出現し、膨張し、もはや、どこからどこまでがアートか分からない状況になりました。
(このあたりの話は非常にスリリングンなのですが、長くなるので割愛します)
フアッションもアート、ポスターもアート、デジタル作品もアート、素人が作ったものもアート。
誰でもアーチィスト!芸能人も、料理人も、花屋も、素人写真家も!
誰もが好きにアートやアーティストを名乗れます。
コーチングの状況も同じですね。
これは何をもたらしたかというと、アートやコーチングの概念の弱体化です。
なんでもアートで、誰でもアーティスト、
なんでもコーチングで、誰でもコーチ、
なら、アートやコーチングとは何か?どういう特徴があるかという、他との差があいまいになり、ブランド的概念の弱体化が起こるということです。
現代アートがよくわからないと言われるのは、難解であるというよりも、基準が一般的にもアート業界にも明確にできないからだと私は思っています。
不自由を創造する
では、以前の様に芸術とは○○だ!と概念の枠組みを明確にし、差別化すればいいのでしょうか?
工業製品や農産物とは違い、私はアートやコーチングでは不可能だと考えます。
なぜなら、枠組み自体が妄想であると、みんなが知ってしまっているからです。いまさら、そのような妄想を語ってももとに戻ることは出来ないでしょう。
では、どのような道があるでしょう?
実はアートの多様化はすでに反動が出てきていて、古典を流用する、古典に乗っかる作品が増えてきています。古典という基準をベースにそこからの逃れ方を見せるというわけです。
よくアーティストの人達がいう言葉に「制約があるから、そこから自由になれる」という物があります。
つまり、なんでもOK、何でも自由と言われる方が何をしていいか判断できず、表現の枠がはずれないというのです。
ある意味、現代のアーティストは自由になるより、いかに不自由になるかが難しいのだと私は考えています。
どのような不自由さを作り出すのか?
今後はそれがアーティストの活躍を決めるものだと私は考えています。
これは、コーチングでも同じです。
コーチングとは○○である!とは、もう誰も定義づけてはくれません。
あなたが自由に好き解釈しコーチングをし、それを活用してもそれほど文句を言われることは無いでしょう。
しかし、その反面コーチングのブランド概念は弱体化してきていることを忘れてはいけません。
私たちは自分自身でコーチングの概念を明確にするために、あえて自分に枠をはめる必要があるのです。
それは、○○コーチングなどとクライアントを限定するという枠ではありません。
そのような下位概念の不自由さはあまり意味を持ちません。
そうではなく、もっと上位概念に不自由さを創造することが必要なのです。
例えば、コーチングかコーチングでないか?という二項対立的な概念を壊し、どちらでもOKと言うのではなく、徹底的にコーチングであり、徹底的にコーチングでないという両極をいつも持ち続けるという考え方です。
私は既存のコーチングを批判しますが、私は本質的にはコーチング根本原理には忠実な人間であると考えています。
世の中は二項対立の分かりやすい世界ではない、それと同時に、なんでもOKの世界でもない。一見、相反する要素を同時に持っています。
明確に区別される世界観とすべてが混沌と混ざり合う世界観これはどちらも正しいのです。
このようになってしまうのは実は「言語」の構造上しかたのないことなのです。(この話もすごく長くなりますのでここでは書きません。また別の機会に書ければと思います)
言葉がなければ私たちは考えることも感情を感じることも出来ません。
しかし、言葉はさまざまな制約や不自由さの中で成り立っています。
言葉の限界が思考の限界なのです。
そのなかで、自由について考えたり、言葉の不自由さについて考えたりしているわけです。
そう、もともと欠陥のある道具や計器を使い、完璧なものを作ろうとしているのと同じです。
しかし、その言葉の不自由さを理解し、それを自分が受け入れることで、言葉の不自由さに気づかなかったときよりも、より自由に人はなれると私は考えています。
アートは言語と非言語の表現をどちらも行いますが、言葉の不自由さを一番感じているにはやはりアーティストだと私は考えます。
だからこそ、アート作品やアーティストを丁寧にみていくことで、コーチングや人間や世界のことをより理解できるのです。