4通目「風雅の便り」
美は心ではなく、言葉で感じるもの
あなたは「美」というものをどんな時に感じますか?
キラキラと輝く夕日を見たとき。
人のために命や人生をささげる人のことを知ったとき。
アート作品や演劇を見たとき。
生命の不思議や物理的な法則を知ったとき。
色々な場面で「美」のようなものを感じたことがあるのではないでしょうか?
しかし、「美」は物質ではありませんので、目に見えるものでも、耳に聞こえるものでもありません。
夕日や芸術作品といったものは、美を宿していると思われるものであって、「美」そのものではありません。
| 言語があるから美が解る |
私達は「美」そのものを五感で感じることができないのに、そこに「美」があると思うのはなぜなのでしょうか?
「心」で感じているのでしょうか?
しかし、「心」には目や耳のような感覚器官はありませんし、そもそも姿形がないものです。
それを感じるとはどういうことなのでしょう?
最先端の美学的に言うとそれは
言葉のシステムが人に「美」を感じさせている、ということです。
言い換えれば「美」を感じるには言葉がなければいけないのです。
そうすると、「いや、言葉で表現できない『美』もある!といわれます。
たしかに、「美」を言葉ですべて表現することはできません。
しかし、
言語を成り立たせているシステムがなければ、私達は「美」の存在にすら気づくことができないのです。
じつは、普段使っている言葉というのは「記号」を「言語システム」の上で動かしているというものです。
この「言語システム」は一般的な文法ではなく、もっと背後で言語をコントロールしているシステムのことです。
例えれば、スマートフォンのプログラムのようなものです。私たちは日常的にスマートフォンを使っていますがそのプログラムのことはほとんど知りません。
しかし、そのプログラムはスマートフォンの動きをすべてコントロールしており、人間の行動までもコントロールしているといえるのです。
例えば、アート関係者同士である絵を見て、
「これ、いいよね!」「そうそう、これいいよね!」
と話が通じあう場合が多いです。でも、業界以外の人にはさっぱり分からないということがあります。
アート関係者は言語ではなく、色や筆づかい構図などという記号を「言語システム」に乗せて読み取ります。
そして、「アート的言語システム」でお互いに会話しているのです。
こういう例はアート業界以外でも起こっています。
「芸術的な感性」とは自分の中に「芸術的言語システム」を作り上げることと言えます。
それは、独りよがりなものではなくて、ある程度他人と共有できるものでなくては意味がありません。
論理的に言語で世界を探求する哲学の一分野として美学があるというのも、
美や感性というものも言語システムにのせないと、評論したり研究出来ないからです。
| 世界を構築している言語システム |
実はこの「言語的システム」を発見したのは現代哲学者です。
この「言語的システム」は芸術だけでなく、政治、経済、人間の思考をバックヤードでコントロールしているシステムなのです。
普段は気づくことができないシステムですが、美学や哲学を学べば、それを見ることができるようになります。
そうすれば、人間のいる世界が多種多様でバラバラなように見えて、突き詰めればある共通点があることがわかります。
よく言われることですが、
様々な分野の一流の人たちが最終的に同じような場所にたどり着くという現象が起こるのです。
その理由は突き詰めればすべての探求は「人間とは?」「世界とは?」「真理とは?」という問いに集約されるからです。
ですから、あなたが今どのような仕事をしていようと、どのような立場や経験があろうと、それを追求しつづければ、結局は同じような回答や問題に行きつくはずです。
さまざまな学問が最終的に行きつく場所を研究しているのが美学や哲学なのです。
なかなか知られていませんが「美学」は奥深いもので、それを形にした芸術作品は本当は哲学的な問いを多く含んだ物なのです。
歴代の哲学者は晩年になってようやく芸術について哲学的に考えるようになると言われます。美学を理解するには哲学の基礎がないと不可能だからです。
| 美学・哲学的アート鑑賞 |
私はアート鑑賞をするとき、作家や年代などの芸術学的なものや美術史的なものにはあまり興味はありません。(もちろん一通りは知っていますが)。
それよりも、
その作品が提示している人間の本質や世界の捉え方に注目します。
それこそ、アート鑑賞の醍醐味です。
ただ残念なのは、
美術館・博物館はそこまで抽象的な鑑賞の仕方を教えません。
近年美術館・博物館への予算が大幅に削られて、予算確保のため広く一般の人達に来場してもらわないといけなくなりました。
そうすると、簡単に解かりやすい!SNS映え!とにかく興味を持ってもらいたいということに流れてしまい、美術館・博物館のアミューズメントパーク化が広まっています。
分かりやすくするというのは大切ですが、それだけではなく、芸術や美の本質を伝えることももっとやって欲しいなと思います。
でも、そうするとお客様は絞られるので、残念ながらやはり数をとれる大衆化に向かっていくのは止められないようにも思います。
私が所属する東京官学支援機構では、文部科学省の施策や提言を知ることができます。
そういった中で国の方針が美術館や学校教育に大きな影響を与えていることが、よくわかります。
国といった大きな枠組みも取り入れた広い視野で「美」について考えれば、自然に社会とは?文化とは?人間とは?という大きなテーマで考えることになります。
私は今の美術館の公開講座や一般の美術講座では教えない抽象度の高い話を、興味を持っていただいた方にはお伝えしていきたいと思っています。
大衆受けはしませんが、人が芸術に限らず、様々な学びを行う上で重要なことですので、日本の未来のためにという志をもってお伝えしていきたいと思います。
次回のお手紙は「美学を人生や仕事を変える道具に変える」についてです。
今回はグッと具体に落としてお伝えします。
美学はそのままでは、人生や仕事に役立てることはできません。
そこには必要なものがあります。
それでは、また。
| ■「風雅の便り」の内容
一通目「なぜなぜ、どうしての美」 (一挙に読みたい方は上記のリンクをクリックすればご覧になれます。理解を深めるため順番通りにお読みください。) |
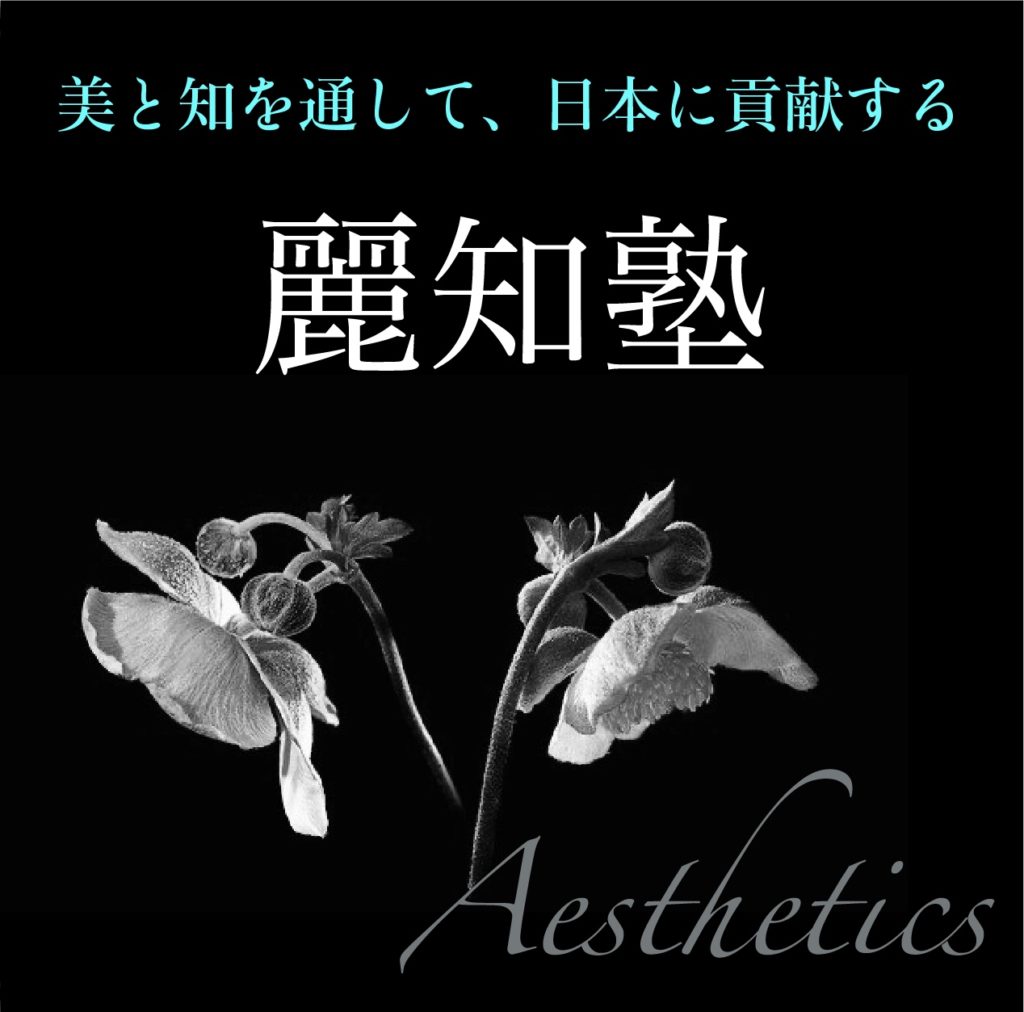
| 麗知塾説明会&ミニ講座 |
参加される方は出来るだけ「風雅の便り」のメール講座(全5回)をご覧になってからご参加ください。
参加費:3000円(事前振り込み)
場所:
【対面】東京 渋谷or新宿又は【オンライン】Zoom
開催時間:2時間
定員:
【対面】各3名(先着順)、【オンライン】個人面談
※お申し込み後に開催場所、ZoomURLはお申込み後お知らせいたします。
申し込み期限:開催日の2日前まで
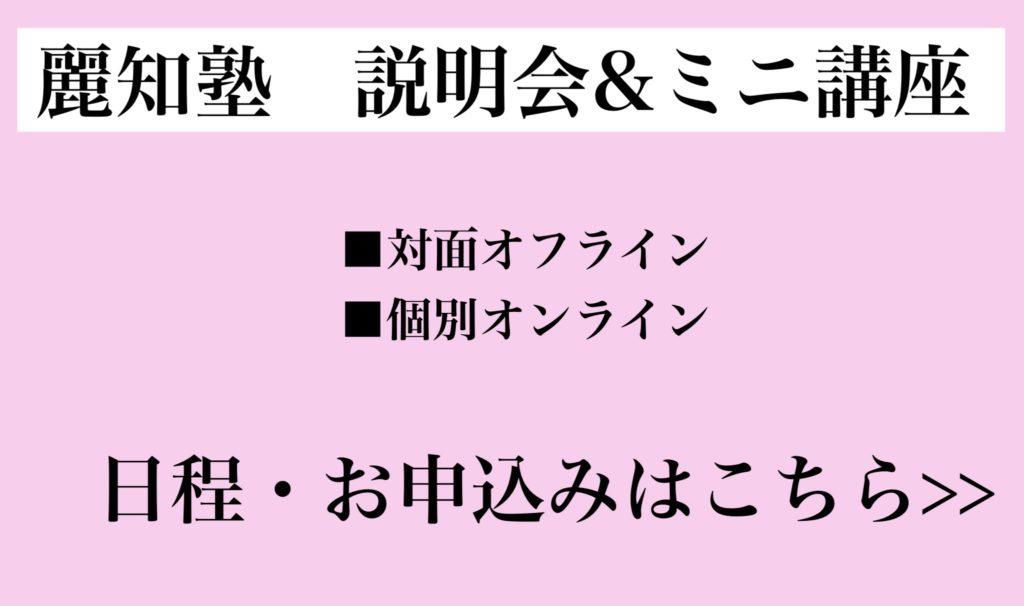
| 麗知塾の内容 |
講座:シーズン1(6回),シーズン2(6回)
- 個別面談(各シーズン6回 対面orオンライン)講座の疑問点、仕事への落とし込み、差別化されたコンテンツ作成、アドバイス、その他。
- 教養基礎講座(解説動画とテキスト資料)
(基礎として知っておくべき哲学、美学、芸術学をメインに提供) - 人文科学・哲学・美学研究における資料
- 課題の提出と個別フィードバック
- 主宰者の哲学・美学・芸術に関する思考コラム
- その他、随時塾生の親睦会等を開催
- シーズン1&シーズン2を受講し、課題提出を終了した方で、希望者には修了書を発行(デジタル)
期間:1年間(シーズン1&2)
料金:説明会でご案内いたします。塾の内容を確認していただいて、必要な方だけに入会していただきたいと思っています。押し売りはいたしません。
【主な講座内容】
■教養基礎講座(シーズン1)
I、理想の美、理想の人間はあるのか?
~理想の自分を追い求める人へ
II、人の痛みや感動を知ることができるのか?
~心理学、感覚の盲点について
III、文系学問は実社会に役立つのか?
~科学的アプローチの死角について
IV、人はなぜ快楽(美)を求めるのか?
~消費社会のビジネスと死との共鳴について
V、弱肉強食の現実社会をどう生きるのか?
~自己成長と妬みの構造について
VI、人生は自分で決めることができるのか?
~人間が生まれながらにもつ自由と罰
————————————————
■教養基礎講座:シーズン2
VII、宇宙は神が作ったのか?そうでないならどのように?
~神と芸術の共存関係について
VIII、マイノリティーは社会的弱者か?
~優劣を逆転させる思想
IX、本当に客観視は出来るのか?
~言葉と感性の間にある曖昧さについて
X、私達の世界はどこまでリアルなのか?
~言語の呪縛から逃れられない人間について
XI、基準のない混沌の世界をどう生きるか?
~固定点を必要としない世界観について
XII、哲学や芸術の終焉?
~終わりの始まりを生きる私たちにとっての教養
現代は科学的なアプローチが支持されている時代です。
科学といえば、人間でさえもモノととらえ、数値化することで客観的な立場で研究することを重視しています。
しかし、究極的には人間は「客観視」などできません。そこにあるのは客観視を目指している「主観」です。
数字やデータに意味を与えるのは人間だからです。
「主観とは何か」を極限まで追求することで、逆に人間が可能な究極的な客観とは何かを理解できるようになります。
この塾ではは科学の有用性を認識しながらも、その限界を明確にすることを美学・哲学を通して行い、自然科学と人文学、客観と主観を包括的に見つめる視点を育成していきます。
また、縦割りの日本のアカデミズムのありかたから脱却すべく、大人が持つべき真のリベラルアーツを美学・哲学を基盤とし提供します。
教材は東京官学支援機構から情報提供を頂いた一般では手に入らない貴重な資料と基本的な哲学・美学の解説とします。
この塾では知識を増やすことではなく、自分の人生や仕事に活用していただき、社会や国に貢献していただくことを重視しています。
そのため自分の頭で考える本当の思考力を磨くためアウトプットも重視しています。
最初は難しく思われるかもしれませんが、何事も初めは初心者です。
一人ではなかなか理解できなくても、マンツーマンであなたの思考力の盲点や成長点について見極め、サポートいたします。
哲学・美学の素晴らしいところは、学べば学んだ分だけ視点が高くなり、視野が広がることです。そして、その視座はあなたが手放さない限り戻ることはありません。
まさに、生涯の指針となるクオリティーのものです。
是非、知と感性を磨き上げてより高い次元の「真善美」をめざしていきましょう。
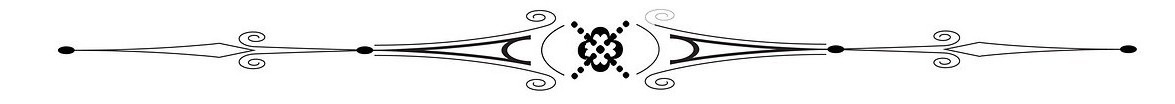
【塾長プロフィール】

石橋ゆかり
麗知塾代表/東京官学支援機構理事
京都市内の京表具師の家に生まれる。同志社大学文学部美学及び芸術学専攻。その後中退し、東京国立能楽(三役)養成所に入所。
6年間能楽太鼓方(金春流)の人間国宝の師匠の下で修業し、修了。
1995年サルサダンス教室を開校。のべ9000人以上にダンス指導(2022年現在)。
2019年アートスクール「美学校」に入校。2年間在籍。
2022年 東京官学支援機構 理事、東京リベラルアーツクラブ(TLC)公認リベラルアーツプロモーター
美学、哲学、芸術学、アートの学びを長年継続。
2022年よりアカデミズムに根差した”美と知”の普及活動を本格始動。
麗知塾を開始
なぜ、私がこのような活動をしているのか
私は小さい頃から、「『美しい』って何だろう?」と考えてきました。生まれたのが京都で両親に連れられて、よく美術館や神社仏閣に行っていたせいかもしれません。
そんな私が今回このような活動を始めた理由は誰かが美やアートの本当の凄みをきちんと伝えなければ、と思ったからです。
実は私は数年前、「アートは世界の本質を伝えてくれますよ」ということを広めようとしていました。
しかし、表現にかかわる仕事をしてきて、長年一流の先生の授業を受けてきたとはいえ大学教授でもない、大学院で正式に学んだこともない私がこんなことを教えていいのだろうか?という思いがありました。
私もビジネスマンですから、他のコンテンツならそんなことは思わなかっただろうと思います。
しかし、「美」や「アート」は私にとって特別な存在なのです。
私は長年学び、経験していく中で芸術、文化が本当は儚いものであり、それが古代から現代まで奇跡的に途切れずに現代まで続き、私達が受け取ることができていることに気づかされました。
先人たちの「美」に対する真摯な態度にただ圧倒され、自分の小ささを思い知らされてきました。
リスペクトする気持ちがあまりに強く、
私などが「美」や「アート」にかかわるなど、とんでもない事柄だという気持ちがあります。
そのため、「美」や「アート」の本質を広めるには、私などよりも適任者がいるのではないかと思っていました。
そうこうしているうちに、「デザイン思考」「アート思考」「対話的鑑賞法」など、アートを現実に落とし込むコンテンツを販売する人や企業も現れ、それに大学の先生方も協力なさっているということを知り、「それなら、私が活動をしなくても、そういう人たちがきちんと伝えたほうがいい。
そのほうが習う人にとってもいいし。」と思いましたので、自分の考えを広める意義もないと思い、やめてしまいました。
しかし、残念なことに様々なアートコンテンツが、結局、「美」や「アート」の本質を伝えることよりも、「楽しく!誰でも簡単に!みんなに親しんでもらえるように!こんなに役立ちます!」というアピール満載で紹介されます。
「美」や「アート」商品化され、薄められ、拡散していきました。
私は本当に、心の底から失望しました。
「なんでこんなに素晴らしいものをそんな売り方で、そんなに中身を薄めて人に紹介できるんだ?」私にはこれは「美」や「アート」に対する裏切りのように思えました。
と同時に、真摯に研究に没頭されている先生方やアーティストに対する裏切りのようにも思えました。
でも多分、そういったアート関連商品を売っている方々に悪意はないのです。その価値をより多くの人たちに伝えたい!という熱意があって、このような形になっているのだと思います。
「美」や「アート」の研究者、専門家といえどもビジネスでは素人です。マーケティングのプロだ!という人から「こうしないと世の中に広まりませんよ。」と言われると、今まで効果のあった、手あかのついた「楽しい、簡単、すぐに」というマーケティングの打ち出し方で商品を売るしかないのだと思います。
それが、「美」や「アート」の本質とは真逆のことでも、一般に広めるには仕方がないと。
でも、そのようなことを放っておくと大人の事情や思惑でゆがめられた「美」や「アート」が、本当なのだと一般の人は誤解してしまいます。
「その程度のモノなのね。」と。
ビジネスはきれいごとだけではないことも、十分承知しています。しかし、この問題は個人的に好き勝手に消費して、汚して、あとは知らないという物でもないと思います。
こう思ってしまったら私はどうしたらいいか?
常々「文句ばっかり言って、何にもしないような生き方はしたくない。」と考え、もうこれは自分でやるしかないと決断しました。
やるからには、出来る限り「美」や「アート」の本質をゆがめたり、自分の都合のいいように作り変えたりしない、そう誓いました。
正直言って、分かってくれる人は少ないでしょう。難しそうだからと敬遠されることも想像できます。
でも、一人でも「美」や「アート」の本質について知りたいという方に、私の今までの知識や経験が役立つのなら、やる意味があると考えています。
私ごときが「美」や「アート」という人類の遺産に対してできることなど、塵(チリ)のようなものですが、知りたいという方がいる限り、全力でお伝えしていこうと思い、こうしてあなたにお話ししているというわけです。
幸い、私は「日本の人文知を守る」という理念のもと寄付活動・研究者支援・普及活動を行う「東京官学支援機構」の理事に就任することになりました。
私たちの団体は大学に代表されるアカデミズムに貢献しますが、それに服従するわけではありません。
究極の目的として、国のために貢献することを重視していますので、アカデミズムに苦言やアドバイスができる立場を確保しています。
そのためにジャーナリズムの役割をにない、出版やデータベース構築を行い、アカデミズムと同様かそれ以上の最上位の情報にアクセスできる立場を確立していきます。
これにより、より正確で、高度な「美と知」に関する情報が手に入るようになりました。
おかげで人に伝える際も、自分の主観で「美」をねじまげる可能性もほぼ無くなります。
東京大学、東京芸術大学からも情報提供をいただいている団体ですので、日本における教育や文化への施策の情報も入ってきますので、日本独自の問題点も高い視点から皆様にお伝えすることができます。
このような日本の人文科学を支援する団体に所属していることで、巡り巡って私の故郷の京都や日本文化を支えることになるというのは、
私の大きなやりがいとなっています。