3通目「風雅の便り」
花と月に美徳を載せて
こんにちは。今日は動画で美しい寮歌をご紹介しますね。
この寮歌は東大駒場(教養学部)の前身校である旧制一高の寮歌で、特によく知られている第十二回紀年祭東寮寮歌です。
漢詩によせた文章で、さすが国家機関に近い大学らしいたたずまいです。
花鳥風月を読み込みながら、これから日本の人々のため、世の中のために学問を学び、粉骨砕身して行くぞという気概と決意が歌われていて、
私は美しさを感じると同時に、
現代の私たちが忘れかけている美徳について考えさせられます。
| 現代のノブレス・オブリージュ |
明治・大正時代、日本が欧州の技術力や文化に追いつき、なんとか日本という国を守ろうとした時代はまさにエリートが活躍しました。
その後、最高学府としての帝国大学(東京大学の前身)が設立され、全国に今ある学校教育システムが導入されていきます。
その選ばれた優秀な人間であるという誇りとその責任感をヒシヒシと感じます。
現在の日本だとエリートというと揶揄するような意味合いで使われることが多いですが、本来エリートというものにはその地位と同等の責任が伴うとされてきました。
欧州に
「ノブレス・オブリージュ」=「高貴さは(義務を)強制する」
という考え方があります。
社会的に高い地位にある者には果たすべき責任があるという考え方です。
日本でも江戸時代には藩校で武芸だけでなく学問を学ぶことが、士族の教育としてなされ、そこで武士としての心構え、立ち振る舞いというエリート教育が行われてきました。
現代においてエリートとはどういう人達でしょう?
昔は身分により社会的役割が決められてきました。
しかし、現代は違います。
日本は民主主義国家で、身分制はありません。
そして、いわゆるエリートの地位とはいえないような一般の人たちの「エリート的な他者への献身の行為」がSNSなどでも目につくようになっています。
つまり、現代のエリートとはある地位にいる特別な人だけが「ノブレス・オブリージュ」を目指すというものではなく、
一般の人たちも「ノブレス・オブリージュ」を体現できるし、それを求められているのではないでしょうか?
実際に天変地異や紛争といった場面で、自分の身を顧みず、他者や地域を守ろうとするごく普通の一般人の行為を私たちはたくさん見てきました。
私たちはそういった
無私の行為に心が引き付けられますし、その行為を美しく感じるのではないでしょうか?
そこに美しさを感じるのは、損得関係を超えた、他者に貢献する行為に高貴さ、普遍性、人間の可能性をそこに見ているからではないでしょうか。
そして、その人自身には損失であっても、そういった行為をすることが人類全体にとっては有益であるだろうという予感があるから、私たちはそこに美を感じるのだと思うのです。
| 美が個人の欲を凌駕する |
その一方で、「個性を大切に生きよう!」「好きな人生を選ぼう!」「他人の価値観に縛られずに生きよう!」
という社会的な立場より個人の欲望をそのまま実現することが良いことという風潮もあります。
個人の欲望と「ノブレス・オブリージュ」がいつも一致するわけではありません。
どちらかを選ばないといけない場面のほうが多いと思います。
人間は基本的には自分個人の欲望を満足させたい生き物です。
小さいときは誰だって自分の好き勝手に、快楽を満たすため欲望全開で生きています。
しかし、大人になるにつれて自分だけのためではなく、自分の欲が少し満たされなくても、他者のために働きたいという人が出てきます。
それはどうしてでしょう?
そういう気持ちも結局は「他人の役に立ちたい!」という自分の欲求を満たしているだけなんだという人もいます。
私はそういうこともあるだろうけれど、
実は「快楽の達成」とは違う基準で人は「ノブレス・オブリージュ」を志すのだと思います。
それは「美」への渇望です。
美しい生き方。美しい魂。美しい立ち振る舞い。そういった
人間を超えた「美」を目指すことで、命に永遠性を取り込みたいという渇望です。
古代においては太陽や山や海などの自然への恐れと崇拝があり、
そういったものから、何か自分では計り知れないものに引き付けられる意識が芽生え、
それが、「美」という物につながって来ているのではないでしょうか?
それは、自分の快楽を満足させるというものではなく、快楽を押さえてでも、「美」という未知のなにかは分からないけれど崇高なものを知りたい、近づきたいという衝動を起こさせるのではないでしょうか。
そして、他者への貢献を意識したとき、自分が薄まり、将来の不安や悩みというものから距離を置くことができるようになります。
つまり、
自分のことばかり心配して行動しているときは不安から逃れられないのに、
自分のことは二の次にして公や美に目を向けたとき、人は不安から逃れることができるようになります。
そういった普遍的な「美」への憧憬や探求心が学問の原点だと私は考えています。
そして、一見自己犠牲に見える行為が、地域、国、人類がより良くなる一助となり、それは巡り巡って、自分の家族や子孫にもその恩恵が降り注ぐことになります。
日本文化の素晴らしさとその高度な抽象度は海外からも認識されています。
しかし、これらの文化は先人方がその技術や思想を絶やしてはいけないと、自分を犠牲にしても、子孫に伝える責任を果たしてくれたからです。
私たちはその恩恵を生まれながらに受けています。それが当たり前に感じてしまいますが、海外ではありえない奇跡的なことなのです。
海外では古代文明は遺跡として、地中から発掘されるものですが、古代文明は日本では生きたものとしてまだ私たちの生活に溶け込んでいます。
奈良の正倉院では今も宝物が当時の姿をとどめたまま保存されています。
これほど古い事物が、脈々と途切れることなく保管され受け継がれているというのは、世界に類を見ないことなのです。これも先人たちが自分が一番かわいいというの快楽欲望にとらわれずに、公の仕事に価値を見出していてくれたからです。
| 日本の人文知を守る |
私が所属している東京官学支援機構では、「国とともに、人文知を守る」という理念のもと、国立大学、行政法人等に寄付を行っています。
これは、
学問における基礎的な研究、それを根本から支えるデータベースこそが日本の要である
という思いからです。
特にすぐに役立つ科学技術などとは違い、手薄になりがちな人文系こそ重要だという理念もあります。
この会の最大の強みは大学の最高地点の知に触れること、行政機関とのパイプがあることではありません。
私たちは大学や行政機関をサポートしつつ、そこに無条件に従うことをよしとしていません。
最大の強みは大学や行政機関に、時には提言をしたり、批判することもいとわないという、超越した第3者の立場を保っていることです。
そのためには金銭的な独立性が必須ですので、結果的に会員はビジネスでしっかりと結果を出し、それによって大きく貢献することが必須となります。
私自身はエリート的な地位はありませんが、志のあるこの会の一員として、美学・哲学をはじめとする人文学に貢献することで、それが日本の文化や教育、日本人の生き方への貢献になると信じています。
次のお手紙の内容は「美は心ではなく、言葉で感じる」です。
一般的に感性と論理は真逆のものだと思われていますが、本当にそうなのか?
感じることや感性についての本質について書きますね。
それでは、また次のお手紙で。
| ■「風雅の便り」の内容
一通目「なぜなぜ、どうしての美」 (一挙に読みたい方は上記のリンクをクリックすればご覧になれます。理解を深めるため順番通りにお読みください。) |
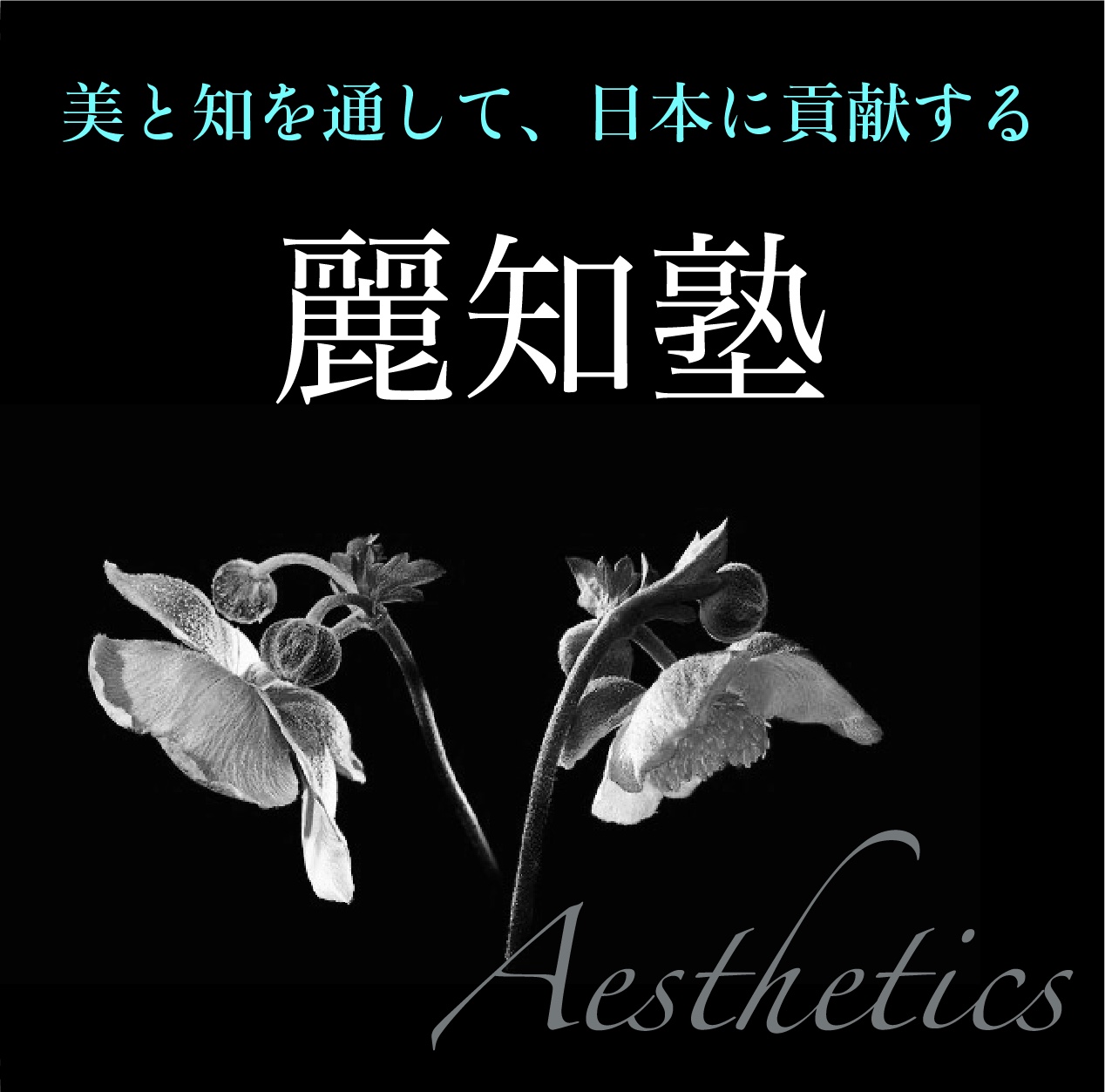
| 麗知塾説明会&ミニ講座 |
参加される方は出来るだけ「風雅の便り」のメール講座(全5回)をご覧になってからご参加ください。
参加費:3000円(事前振り込み)
場所:
【対面】東京 渋谷or新宿又は【オンライン】Zoom
開催時間:2時間
定員:
【対面】各3名(先着順)、【オンライン】個人面談
※お申し込み後に開催場所、ZoomURLはお申込み後お知らせいたします。
申し込み期限:開催日の2日前まで
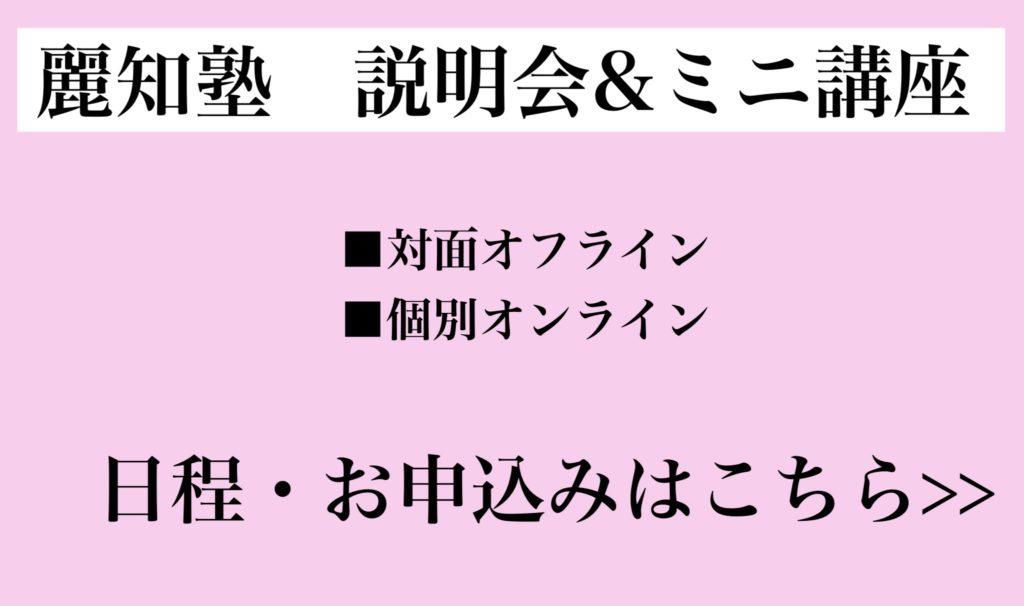
| 麗知塾の内容 |
講座:シーズン1(6回),シーズン2(6回)
- 個別面談(各シーズン6回 対面orオンライン)講座の疑問点、仕事への落とし込み、差別化されたコンテンツ作成、アドバイス、その他。
- 教養基礎講座(解説動画とテキスト資料)
(基礎として知っておくべき哲学、美学、芸術学をメインに提供) - 人文科学・哲学・美学研究における資料
- 課題の提出と個別フィードバック
- 主宰者の哲学・美学・芸術に関する思考コラム
- その他、随時塾生の親睦会等を開催
- シーズン1&シーズン2を受講し、課題提出を終了した方で、希望者には修了書を発行(デジタル)
期間:1年間(シーズン1&2)
料金:説明会でご案内いたします。塾の内容を確認していただいて、必要な方だけに入会していただきたいと思っています。押し売りはいたしません。
【主な講座内容】
■教養基礎講座(シーズン1)
I、理想の美、理想の人間はあるのか?
~理想の自分を追い求める人へ
II、人の痛みや感動を知ることができるのか?
~心理学、感覚の盲点について
III、文系学問は実社会に役立つのか?
~科学的アプローチの死角について
IV、人はなぜ快楽(美)を求めるのか?
~消費社会のビジネスと死との共鳴について
V、弱肉強食の現実社会をどう生きるのか?
~自己成長と妬みの構造について
VI、人生は自分で決めることができるのか?
~人間が生まれながらにもつ自由と罰
————————————————
■教養基礎講座:シーズン2
VII、宇宙は神が作ったのか?そうでないならどのように?
~神と芸術の共存関係について
VIII、マイノリティーは社会的弱者か?
~優劣を逆転させる思想
IX、本当に客観視は出来るのか?
~言葉と感性の間にある曖昧さについて
X、私達の世界はどこまでリアルなのか?
~言語の呪縛から逃れられない人間について
XI、基準のない混沌の世界をどう生きるか?
~固定点を必要としない世界観について
XII、哲学や芸術の終焉?
~終わりの始まりを生きる私たちにとっての教養
現代は科学的なアプローチが支持されている時代です。
科学といえば、人間でさえもモノととらえ、数値化することで客観的な立場で研究することを重視しています。
しかし、究極的には人間は「客観視」などできません。そこにあるのは客観視を目指している「主観」です。
数字やデータに意味を与えるのは人間だからです。
「主観とは何か」を極限まで追求することで、逆に人間が可能な究極的な客観とは何かを理解できるようになります。
この塾ではは科学の有用性を認識しながらも、その限界を明確にすることを美学・哲学を通して行い、自然科学と人文学、客観と主観を包括的に見つめる視点を育成していきます。
また、縦割りの日本のアカデミズムのありかたから脱却すべく、大人が持つべき真のリベラルアーツを美学・哲学を基盤とし提供します。
教材は東京官学支援機構から情報提供を頂いた一般では手に入らない貴重な資料と基本的な哲学・美学の解説とします。
この塾では知識を増やすことではなく、自分の人生や仕事に活用していただき、社会や国に貢献していただくことを重視しています。
そのため自分の頭で考える本当の思考力を磨くためアウトプットも重視しています。
最初は難しく思われるかもしれませんが、何事も初めは初心者です。
一人ではなかなか理解できなくても、マンツーマンであなたの思考力の盲点や成長点について見極め、サポートいたします。
哲学・美学の素晴らしいところは、学べば学んだ分だけ視点が高くなり、視野が広がることです。そして、その視座はあなたが手放さない限り戻ることはありません。
まさに、生涯の指針となるクオリティーのものです。
是非、知と感性を磨き上げてより高い次元の「真善美」をめざしていきましょう。
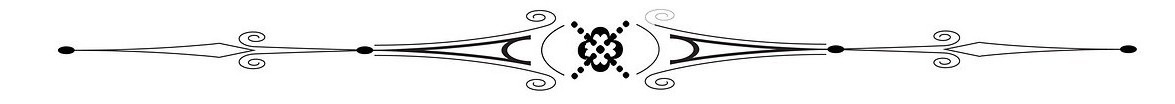
【塾長プロフィール】

石橋ゆかり
麗知塾代表/東京官学支援機構理事
京都市内の京表具師の家に生まれる。同志社大学文学部美学及び芸術学専攻。その後中退し、東京国立能楽(三役)養成所に入所。
6年間能楽太鼓方(金春流)の人間国宝の師匠の下で修業し、修了。
1995年サルサダンス教室を開校。のべ9000人以上にダンス指導(2022年現在)。
2019年アートスクール「美学校」に入校。2年間在籍。
2022年 東京官学支援機構 理事、東京リベラルアーツクラブ(TLC)公認リベラルアーツプロモーター
美学、哲学、芸術学、アートの学びを長年継続。
2022年よりアカデミズムに根差した”美と知”の普及活動を本格始動。
麗知塾を開始
なぜ、私がこのような活動をしているのか
私は小さい頃から、「『美しい』って何だろう?」と考えてきました。生まれたのが京都で両親に連れられて、よく美術館や神社仏閣に行っていたせいかもしれません。
そんな私が今回このような活動を始めた理由は誰かが美やアートの本当の凄みをきちんと伝えなければ、と思ったからです。
実は私は数年前、「アートは世界の本質を伝えてくれますよ」ということを広めようとしていました。
しかし、表現にかかわる仕事をしてきて、長年一流の先生の授業を受けてきたとはいえ大学教授でもない、大学院で正式に学んだこともない私がこんなことを教えていいのだろうか?という思いがありました。
私もビジネスマンですから、他のコンテンツならそんなことは思わなかっただろうと思います。
しかし、「美」や「アート」は私にとって特別な存在なのです。
私は長年学び、経験していく中で芸術、文化が本当は儚いものであり、それが古代から現代まで奇跡的に途切れずに現代まで続き、私達が受け取ることができていることに気づかされました。
先人たちの「美」に対する真摯な態度にただ圧倒され、自分の小ささを思い知らされてきました。
リスペクトする気持ちがあまりに強く、
私などが「美」や「アート」にかかわるなど、とんでもない事柄だという気持ちがあります。
そのため、「美」や「アート」の本質を広めるには、私などよりも適任者がいるのではないかと思っていました。
そうこうしているうちに、「デザイン思考」「アート思考」「対話的鑑賞法」など、アートを現実に落とし込むコンテンツを販売する人や企業も現れ、それに大学の先生方も協力なさっているということを知り、「それなら、私が活動をしなくても、そういう人たちがきちんと伝えたほうがいい。
そのほうが習う人にとってもいいし。」と思いましたので、自分の考えを広める意義もないと思い、やめてしまいました。
しかし、残念なことに様々なアートコンテンツが、結局、「美」や「アート」の本質を伝えることよりも、「楽しく!誰でも簡単に!みんなに親しんでもらえるように!こんなに役立ちます!」というアピール満載で紹介されます。
「美」や「アート」商品化され、薄められ、拡散していきました。
私は本当に、心の底から失望しました。
「なんでこんなに素晴らしいものをそんな売り方で、そんなに中身を薄めて人に紹介できるんだ?」私にはこれは「美」や「アート」に対する裏切りのように思えました。
と同時に、真摯に研究に没頭されている先生方やアーティストに対する裏切りのようにも思えました。
でも多分、そういったアート関連商品を売っている方々に悪意はないのです。その価値をより多くの人たちに伝えたい!という熱意があって、このような形になっているのだと思います。
「美」や「アート」の研究者、専門家といえどもビジネスでは素人です。マーケティングのプロだ!という人から「こうしないと世の中に広まりませんよ。」と言われると、今まで効果のあった、手あかのついた「楽しい、簡単、すぐに」というマーケティングの打ち出し方で商品を売るしかないのだと思います。
それが、「美」や「アート」の本質とは真逆のことでも、一般に広めるには仕方がないと。
でも、そのようなことを放っておくと大人の事情や思惑でゆがめられた「美」や「アート」が、本当なのだと一般の人は誤解してしまいます。
「その程度のモノなのね。」と。
ビジネスはきれいごとだけではないことも、十分承知しています。しかし、この問題は個人的に好き勝手に消費して、汚して、あとは知らないという物でもないと思います。
こう思ってしまったら私はどうしたらいいか?
常々「文句ばっかり言って、何にもしないような生き方はしたくない。」と考え、もうこれは自分でやるしかないと決断しました。
やるからには、出来る限り「美」や「アート」の本質をゆがめたり、自分の都合のいいように作り変えたりしない、そう誓いました。
正直言って、分かってくれる人は少ないでしょう。難しそうだからと敬遠されることも想像できます。
でも、一人でも「美」や「アート」の本質について知りたいという方に、私の今までの知識や経験が役立つのなら、やる意味があると考えています。
私ごときが「美」や「アート」という人類の遺産に対してできることなど、塵(チリ)のようなものですが、知りたいという方がいる限り、全力でお伝えしていこうと思い、こうしてあなたにお話ししているというわけです。
幸い、私は「日本の人文知を守る」という理念のもと寄付活動・研究者支援・普及活動を行う「東京官学支援機構」の理事に就任することになりました。
私たちの団体は大学に代表されるアカデミズムに貢献しますが、それに服従するわけではありません。
究極の目的として、国のために貢献することを重視していますので、アカデミズムに苦言やアドバイスができる立場を確保しています。
そのためにジャーナリズムの役割をにない、出版やデータベース構築を行い、アカデミズムと同様かそれ以上の最上位の情報にアクセスできる立場を確立していきます。
これにより、より正確で、高度な「美と知」に関する情報が手に入るようになりました。
おかげで人に伝える際も、自分の主観で「美」をねじまげる可能性もほぼ無くなります。
東京大学、東京芸術大学からも情報提供をいただいている団体ですので、日本における教育や文化への施策の情報も入ってきますので、日本独自の問題点も高い視点から皆様にお伝えすることができます。
このような日本の人文科学を支援する団体に所属していることで、巡り巡って私の故郷の京都や日本文化を支えることになるというのは、
私の大きなやりがいとなっています。